虫歯や歯周病が進行し、抜歯を余儀なくされたとき、その後どうするかは重要な選択になります。
入れ歯やブリッジと並んで、インプラント治療を検討する人も少なくありません。
しかし「抜歯のあと、いつインプラントをすればいいのか?」と迷う方は多いはずです。
治療のタイミングは、見た目や噛む力だけでなく、将来的な歯や骨の健康にも影響します。
今回は、抜歯後のインプラントについて、基本的な知識と注意点をご紹介します。
抜歯後にインプラント治療を行う理由とは

*抜歯後に放置すると起きること
歯を失ったまま長期間放置すると、顎の骨が徐々に痩せてしまいます。
歯がなくなることで噛む刺激が伝わらなくなり、骨が役割を失って吸収されてしまうのです。
また、隣の歯が傾いてきたり、噛み合わせのバランスが崩れたりと、口腔全体に悪影響が広がります。
これらの変化は自然には元に戻らず、インプラント治療にも支障をきたすことがあります。
*インプラントが抜歯後の選択肢になる理由
インプラントは、抜歯後に生じる骨や歯並びの変化を防ぎやすい治療法です。
顎の骨に人工の歯根を埋め込むことで、見た目や噛む力を回復できるだけでなく、骨への刺激を保つことも可能です。
入れ歯やブリッジに比べ、周囲の健康な歯を削らずに済む点も大きな利点となります。
*インプラント治療の基本的な流れ
インプラント治療は、診断から手術、定着期間、上部構造の装着まで、段階的に進みます。
まずCTなどで骨の状態を確認し、問題がなければインプラント体の埋入手術を行います。
その後、骨と結合するまで数ヶ月待機し、安定した段階で人工歯を取り付けます。
治療期間は個人差がありますが、全体で3〜6ヶ月以上を要するのが一般的です。
抜歯後のインプラント治療はタイミングが重要

*即時埋入と待時埋入の違い
インプラントの埋入時期には「即時埋入」と「待時埋入」があります。
即時埋入は、抜歯と同時にインプラントを埋め込む方法です。
一方、待時埋入は抜歯後の治癒期間(通常2〜3ヶ月)を待ってから手術を行います。
どちらの方法も確立された治療法であり、患者の状態によって使い分けられます。
*それぞれのメリットとリスク
即時埋入の最大の利点は、治療期間の短縮と骨吸収の抑制です。
ただし、炎症が残っていると感染リスクが高まるため、適応には条件があります。
待時埋入は治癒後に手術を行うため、安全性が高く、術後の安定も得やすい反面、治療期間は長くなります。
どちらを選ぶかは、口腔内の状態と希望を踏まえた総合判断となります。
*タイミングの判断に影響する要素
埋入タイミングの決定には、歯周病や炎症の有無、抜歯部位の骨の厚み、全身疾患の有無などが関わります。
また、喫煙習慣や歯ぎしりなどの生活習慣も考慮されます。
適切なタイミングで治療を受けるには、信頼できる歯科医師との十分な相談が欠かせません。
抜歯からインプラントまでに気をつけること

*治療前に確認すべき口腔内の状態
インプラント治療を成功させるには、清潔な口腔環境が不可欠です。
歯周病や虫歯がある状態では、感染リスクが高まります。
事前にスケーリングなどで口腔内を整えておくことが推奨されます。
また、骨量が不足している場合には骨造成などの処置が必要となることもあります。
*抜歯後に避けるべき生活習慣
抜歯後の患部はとても繊細な状態です。
激しいうがいや飲酒、喫煙、過度な運動は出血や感染の原因となるため避けましょう。
また、食事も片側で噛むようにし、患部に強い刺激を与えないことが大切です。
治癒を早めるには、睡眠や栄養にも気を配る必要があります。
*歯科医院選びで意識したいポイント
インプラント治療は高度な技術と判断力が求められるため、経験豊富な歯科医院を選ぶことが重要です。
治療実績やカウンセリングの丁寧さ、CTなどの設備の有無などを確認しましょう。
また、術後のフォロー体制も含めて、長く付き合える医院かどうかも見極めたいポイントです。
まとめ
抜歯後のインプラント治療では、タイミングの選択が結果を左右します。
即時埋入と待時埋入にはそれぞれ特徴があり、患者の口腔内の状態や希望に応じて適した方法が選ばれます。
抜歯後は骨や歯並びへの悪影響を防ぐため、できるだけ早く治療方針を立てることが望ましいです。
治療前の準備や生活管理、歯科医院の選び方も成功のカギとなります。
安心して治療に進めるよう、まずは信頼できる歯科医師に相談してみましょう。


 ご予約はこちら
ご予約はこちら

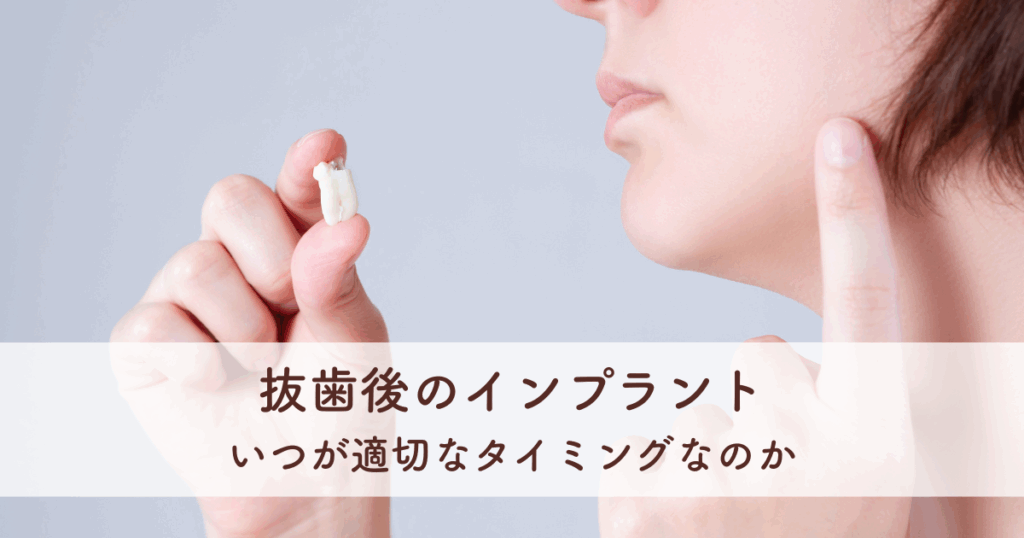
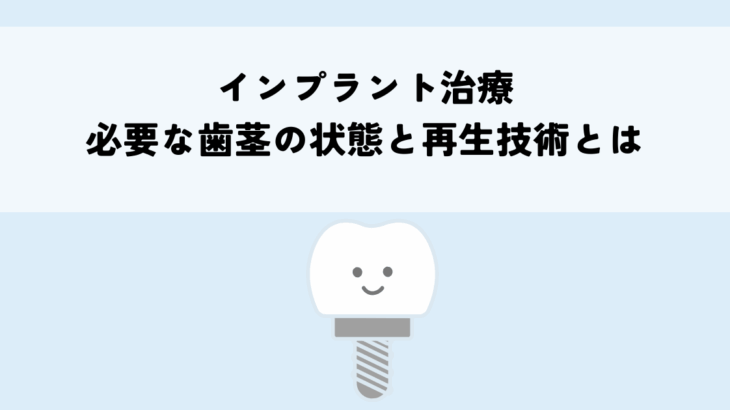
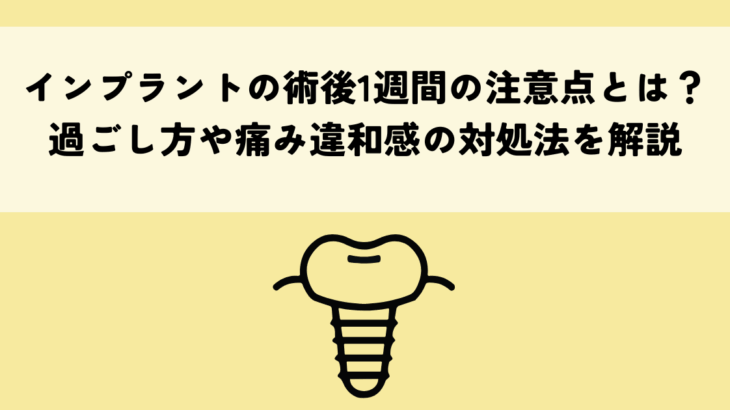
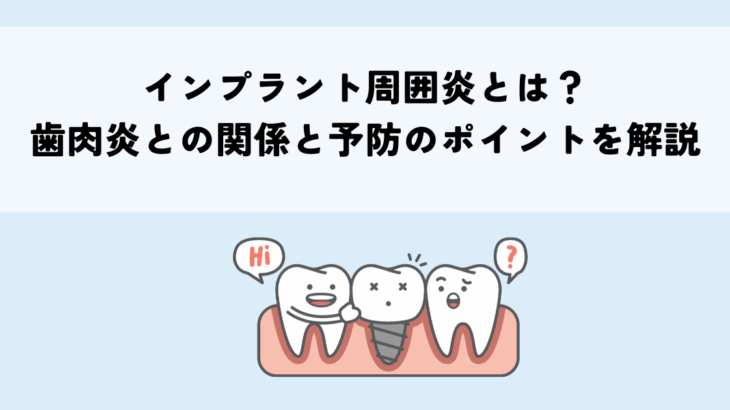
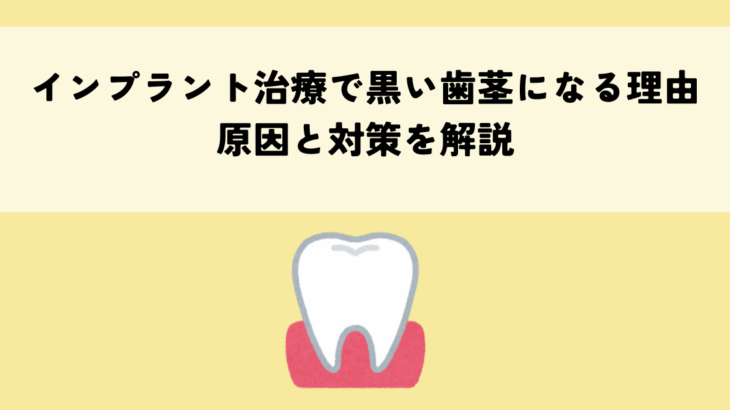
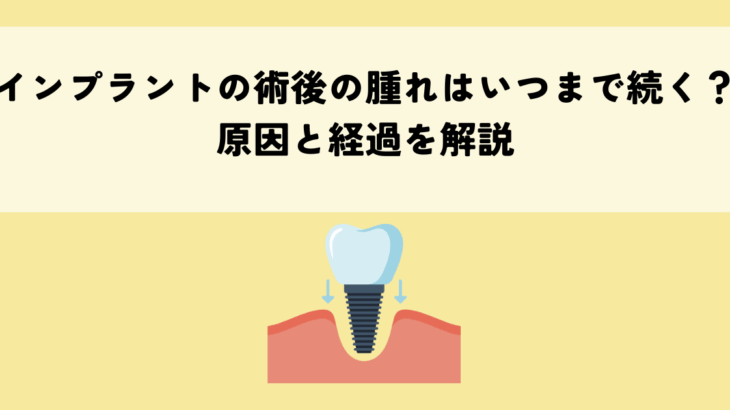
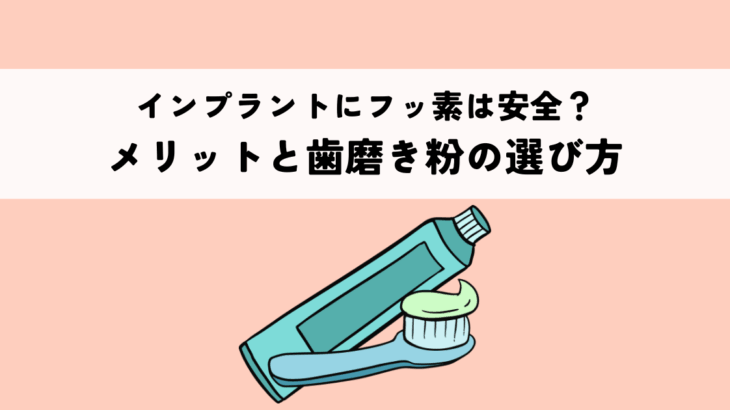
 LINE相談
LINE相談