親知らずの抜歯を勧められた際、「神経に近い」と言われて不安になった経験はありませんか。
見えない部分だからこそ、どれほどのリスクがあるのか想像しづらいものです。
抜歯後の麻痺やしびれといった後遺症の可能性も耳にすることがあり、不安が増す方も多いでしょう。本記事では、親知らずと神経の関係から、抜歯による影響、事前にできる対策までを順を追ってご紹介します。
大切な判断の一助となれば幸いです。
親知らずと神経の位置関係について理解する

*下顎管と下歯槽神経の基礎知識
親知らずと関わりが深い神経のひとつに、下顎管内を通る下歯槽神経があります。
この神経は顎の骨の中を走り、下の奥歯の感覚を支配しています。
特に下顎の親知らずは、この神経と距離が近くなることが多く、位置関係によっては抜歯時に神経を刺激する可能性もあります。
骨の中にあるため見えませんが、非常に重要な部位です。
*親知らずが神経に近いとはどういう状態か
歯の根が神経と接している、もしくは重なっているような状態を「神経に近い」と表現します。
中でも歯根と神経が交差していたり、薄い骨を挟むだけで隣接していたりすると、抜歯の際に神経に影響を与えるリスクが高まります。
歯の角度や根の形によっても距離感が変わるため、患者ごとに状況は異なります。
*神経に近いかどうかの診断方法
一般的なレントゲンでは神経との距離をある程度把握できますが、より正確な診断にはCT(3D画像撮影)が有効です。
CTを使えば神経の位置や親知らずの根の形状を立体的に確認でき、リスクの高いケースかどうかをより正確に判断できます。
抜歯の前にはこの診断ステップが欠かせません。
神経に近い親知らずを抜くときのリスクと判断基準

*抜歯による神経損傷の可能性
神経が近い状態で無理に抜歯を行うと、神経が傷ついたり圧迫されたりするリスクがあります。
こうした損傷が起きた場合、下唇や顎、舌のしびれなどが生じることがあり、数週間から長ければ数年、あるいは永久的に症状が残るケースもあります。
ただし、すべての神経近接ケースが抜歯不可というわけではなく、診断によって適切な処置が選ばれます。
*術後に起こりうる麻痺やしびれの実態
術後に生じる感覚異常には、麻酔の影響による一時的なものと、神経損傷による長期的なものがあります。
前者は通常数時間から数日で回復しますが、後者の場合、しびれや鈍麻(感覚が鈍い状態)が数ヶ月残ることもあります。
特に下唇の感覚に違和感を覚える例が報告されています。
完全な麻痺に至るケースはまれですが、注意が必要です。
*抜歯を回避・延期する判断基準
リスクが高いと判断された場合には、無理に抜歯せず経過観察を選択することもあります。
また、痛みや炎症がない限り、抜歯を急がずにタイミングを見計らうという方法もあります。
歯の状態や年齢、全身の健康状態を総合的に考慮し、必要に応じて専門医の意見を仰ぐことが勧められます。
親知らずの抜歯前後にできるリスク管理の工夫

*事前に確認すべき医師の説明ポイント
抜歯を検討する際には、神経への距離やリスクの程度、抜歯方法の選択肢、術後の経過予想などについて丁寧な説明を求めることが大切です。
不安に思う点は遠慮せずに質問し、納得したうえで処置に臨むことが望まれます。
医師との信頼関係が、治療結果にも大きく影響します。
*CT撮影によるリスク予測の重要性
CTは親知らずの抜歯リスクを数値化・可視化するのに非常に有効です。
2Dのレントゲンでは判別できない根の湾曲や神経との交差なども、CTなら明確に捉えられます。
歯科医院によっては提携施設で撮影するケースもあるため、事前に設備の有無も確認しておくと安心です。
*神経に近い親知らずへの対応経験が豊富な歯科医院の選び方
神経に近い親知らずの抜歯は、外科的判断と経験値が求められる処置です。
口腔外科を標榜している医院や、難症例に対応してきた実績のある歯科医院を選ぶことが推奨されます。
初診時の対応や説明の丁寧さも、信頼できる医院かどうかを見極める指標のひとつになります。
まとめ
親知らずが神経に近いと診断された場合、まずは神経の位置関係を理解することが第一歩です。
抜歯には神経損傷のリスクがある一方で、CT撮影などの精密な診断によって、安全に進める道もあります。
医師の説明をよく聞き、不安を解消しながら慎重に判断していくことが大切です。
自身の状況に合った適切な対策で、納得のいく選択をしましょう。


 ご予約はこちら
ご予約はこちら

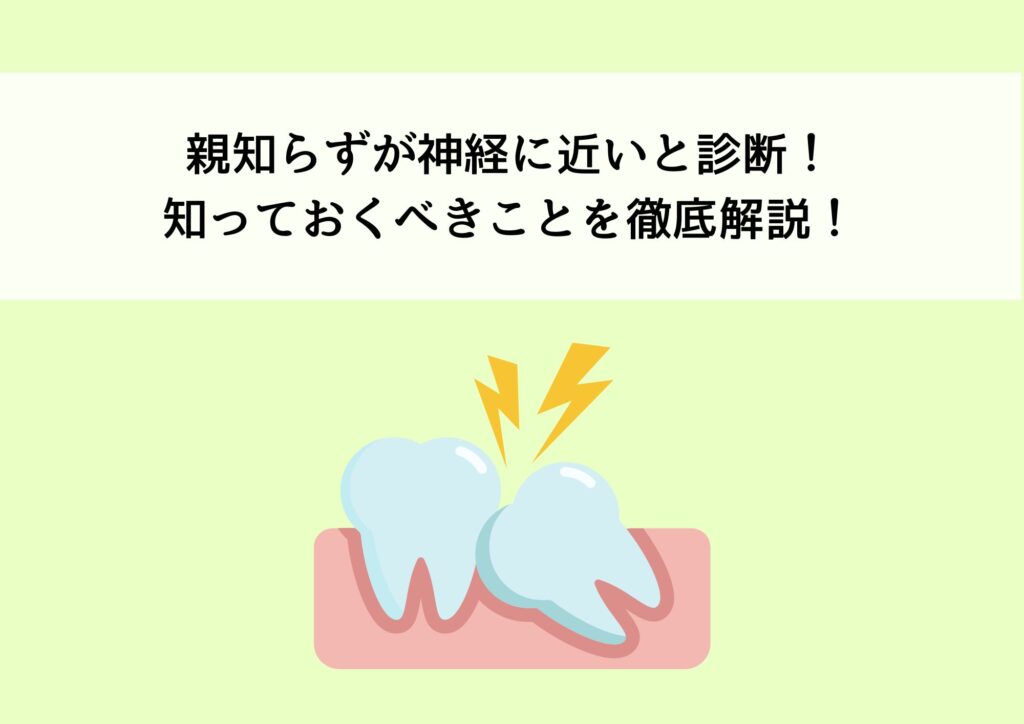
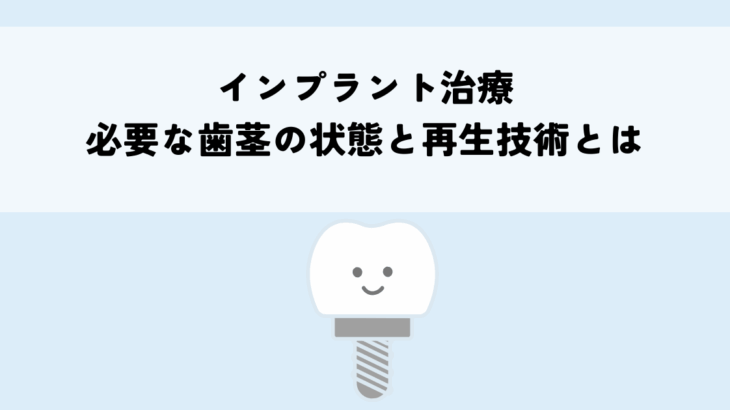
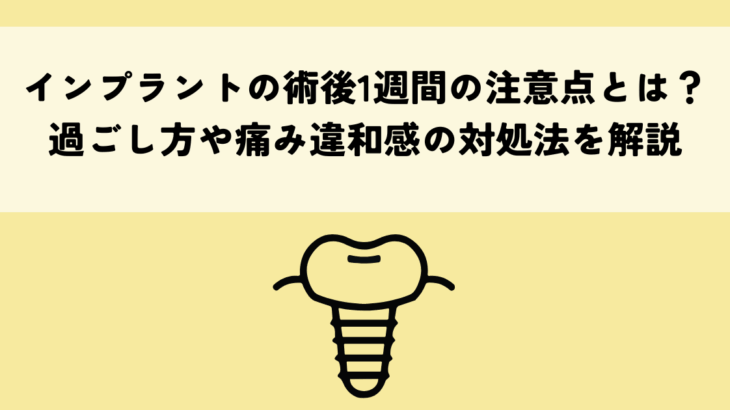
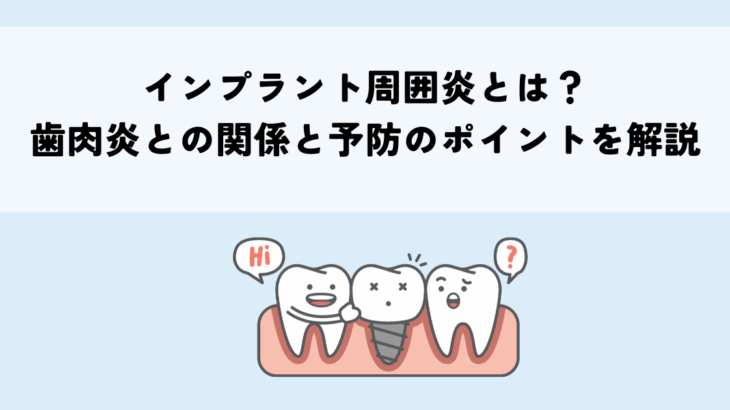
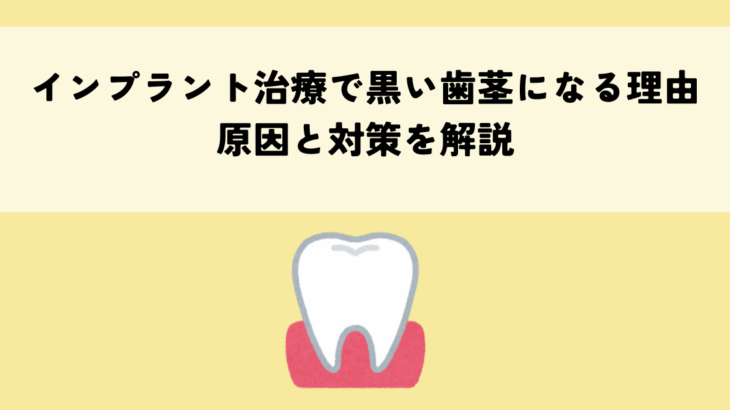
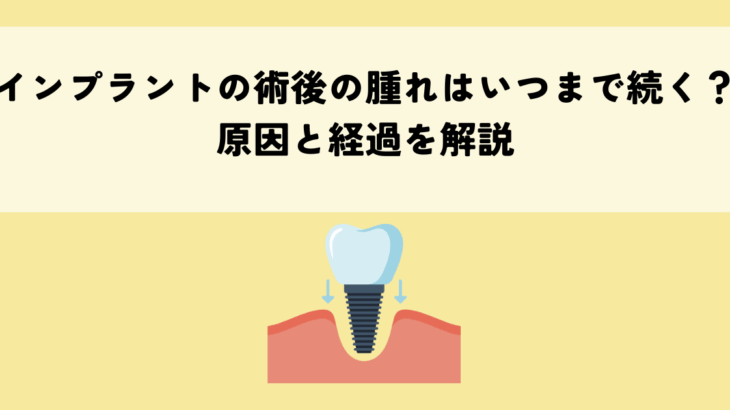
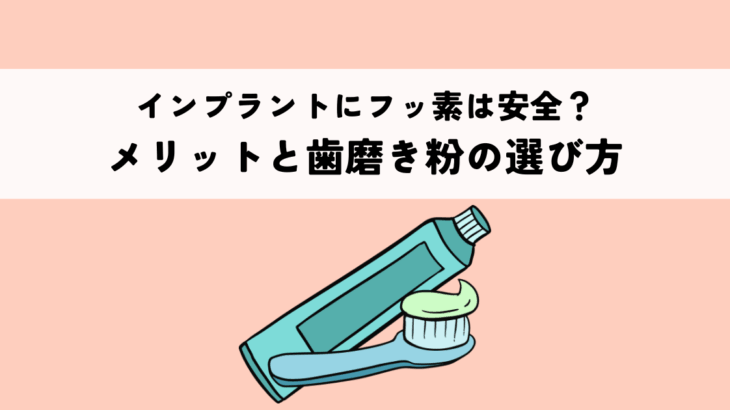
 LINE相談
LINE相談